環境教育の難しさ【2017/6/29】
[ ■ 日々の事 ]
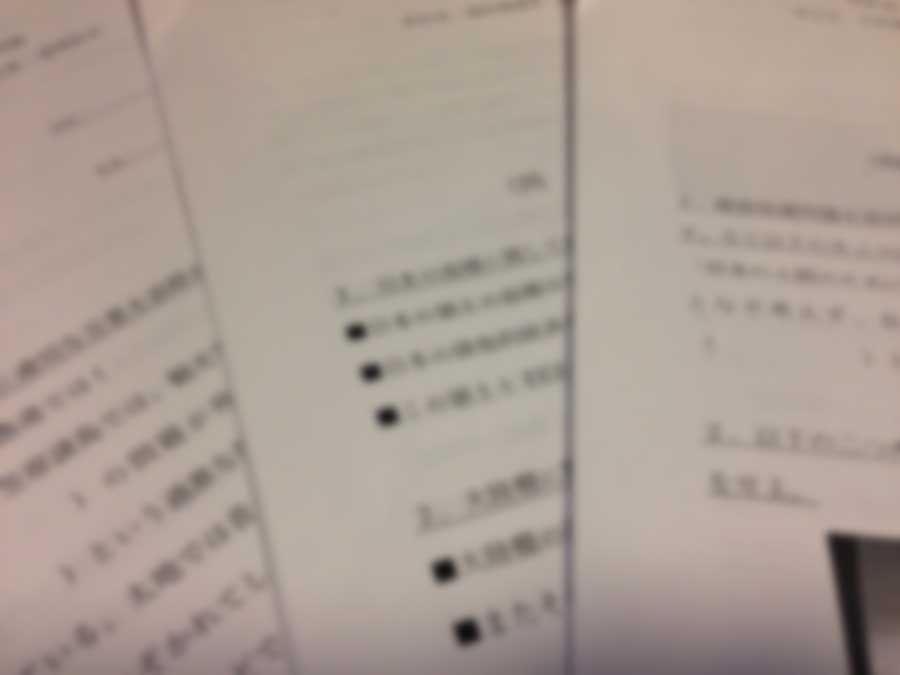
僕の専門学校では来週から前期試験です。授業分の三つの問題を作成しました(なので問題はぼかしてます)。
ここまで授業をやってきて考えさせられたことがある。生物多様性は危機にあって、それには「第1の危機」から「第4の危機」までがあると国際的に一致した意見がある。「第1の危機」は「人間による開発と乱獲」。「第2の危機」はその逆で「人間による自然への手入れ不足」、つまり里地里山の問題に当たる。学生たちは「第1の危機」に関しては理解できるようだが、それと矛盾しているように見える「第2の危機」に関しては理解できないようだ。「なんで自然を守ろうとしているのに、人の手入れ不足が問題になるんだ?」というのが学生たちの、と言うか今の若い子の意見なのだ。
「体験格差」という言葉もあるようだ。幼少期に親がどれだけのことを経験させるかによってその子供の将来が変わってくるようだ。
「第1の危機」と「第2の危機」が矛盾しているというのは、もしかしたら子供の頃自然のある場所や動物園などに連れて行ってもらえなかった可能性もある。正直自分も田舎暮らしなどちょっと遠い話だけどね。
お金が全てではないが、この前スライドやったナカメの保育園は土地柄、裕福な親が多く「案外水族館や海外に連れて行ってもらってる園児もいます」と園長先生は言ってた。それだけに園児の反応大きかった。なので必ず1年生のテスト問題には富士講の話を問題に入れている。将来動物を管理(ある種隔離)する仕事を希望する子が多いので、富士講は日本人と自然との関わりがもっともわかるものだと思っているからだ。実に難しく深刻な問題だ。
